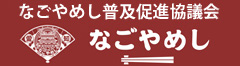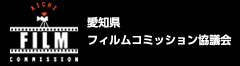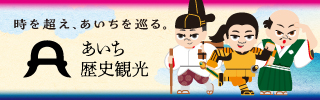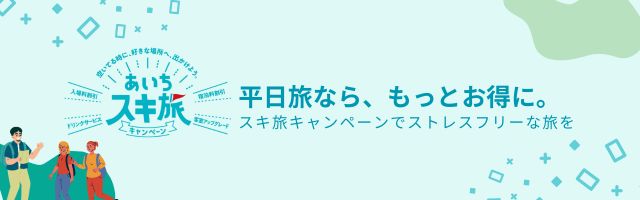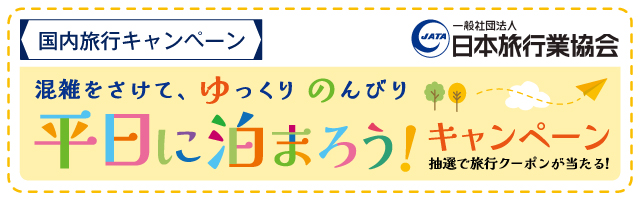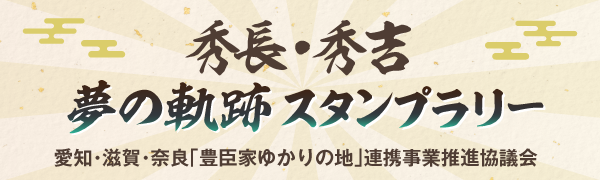第34回 吉田文楽保存会定期公演(よしだぶんらくほぞんかいていきこうえん)
【このイベントは終了しました。】開催日 : 2025年11月16日
文楽は歌舞伎や能と並び、日本を代表する伝統芸能の一つ。感情たっぷりに物語を伝える太夫の語りと三味線の演奏に合わせて、人形遣いが1体の人形を3人で操る人形芝居です。
約400年以上前から受け継がれる豊橋市指定無形民俗文化財「飽海人形浄瑠璃(通称:吉田文楽)」の定期公演が開催されます。
ご家族、お友達と一緒に、ぜひこの機会に総合芸術に触れてみてください。
演目
◎二人三番叟(ににんさんばそう)
三番叟は五穀豊穣・子孫繁栄を願う舞いで、今ではその華やかさから劇場の開場や正月など祝賀行事の最初の出し物として取り上げられます。
今回は、右手に鈴、左手に扇を持って舞う場面の上演です。
途中、種まきの所作がありますが、これは農作業と同じ動作を模することで豊作を祈願するものです。一人が疲れて休もうとするところを、もう一人が励ましつつも自分もこっそり休むという滑稽な場面を挟んで、華やかに舞い納めます。
◎お弓橋心中 お弓橋の段(おゆみばししんじゅう おゆみばしのだん)
今年度人形初披露となるこの演目は、令和3年度に豊橋市が実施した「伝統芸能後継者育成事業」において講師を務めた、人形浄瑠璃文楽座の豊竹藤太夫、鶴澤清志郎両師匠により教材として作られたものです。
題材は地域に残る伝承であり、飽海人形浄瑠璃とも関連の深い民話「お弓橋」を選定し作成されました。
お弓橋は、牛川薬師町と御園町の間を流れる朝倉川に架かる現存する橋であり、牛川村のお弓と瓦町の京之介が吉田城下で繰り広げる悲しい恋の物語です。
◎傾城阿波の鳴門 順礼歌の段(けいせいあわのなると じゅんれいうたのだん)
徳島藩のお家騒動を題材にした十段の浄瑠璃で、現在では八段目前半の「順礼歌の段」が主に上演されています。明和五年(1768)大坂竹本座で初演されました。
お弓がお鶴を我が子と知りながら、自分たちが盗賊の一味であるために災難がかかってはと、追い返すシーンが有名です。「親たちの名は‥」と問うお弓に、お鶴が「とと様の名は十郎兵衛、かか様はお弓と申します。」と答える様が哀れで涙を誘います。お鶴を追い返した後のお弓のクドキでクライマックスを迎えます。
イベントの概要 outline
- 開催日
- 2025年11月16日(日)
- 開催時間
- 【開場】13:00
【開演】13:30(途中入場可) - 開催場所
- 豊橋市公会堂 大ホール
- 所在地
- 〒440-0806
豊橋市八町通2丁目22番地 - 料金
- 入場無料
※ 料金は変更になる可能性がございますので公式サイト等でご確認ください
- トイレ
- 有り
- お問い合わせ
- 0532-88-4651(吉田文楽保存会(浦川))
※ 留守番電話に入れてください - 駐車場
- 無し
※ 市役所駐車場をご利用ください
アクセス方法access
-

電車でのアクセス
JR東海道線(豊橋行)、名鉄名古屋本線(豊橋行)「名古屋」駅から「豊橋」駅にて豊橋鉄道市内線(赤岩口・運動公園前行)に乗り換え、「市役所前」駅にて下車。徒歩2分